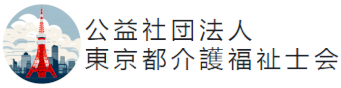国際事業部
[目的]
o 日本人介護職員と外国人介護職員の相互理解を深め、介護現場での協働を進める。
o ともに学びあうことを通じて、日本の介護について客観的にとらえ、考え直す。
o 海外で活動する介護福祉士や現地の介護職員等と交流し、ネットワークを作る。
[活動内容(2023年現在)]
ミャンマー、中国出身の委員やベトナムで活動する委員、介護施設や介護福祉士養成校等で外国人介護職員・留学生と接している委員など多彩なメンバーが、お互いの知見を活かした活動をしています。
- 定例ミーティング(学習会・情報共有・活動うちあわせ)
- 外国人介護職員・留学生との交流会、学習会
- 日本人職員が外国人介護職員と協働するためのセミナー
- 海外で活動する日本人介護福祉士等との交流
- SNSによる日本語を母語としない介護職員向け情報発信
- 国際事業部の活動の長期ビジョンづくり
[これまでの主な活動]
o 2012年に国際協力委員会として発足(2018年6月に国際事業部に名称変更)、外国人介護職員や日本人支援者等を招いてのセミナーを継続的に開催。
o EPA候補者対象の介護福祉士国家試験模擬試験解説講座(2013年)
o 技能実習制度による介護人材の受け入れを考えるシンポジウム(2014年)
o 大塚モスク見学ツアー、支援活動(2018年)
[定例ミーティング 資料]
- どうなる?外国人介護職員の就労の仕組み(2024.1.10) 詳細はこちら